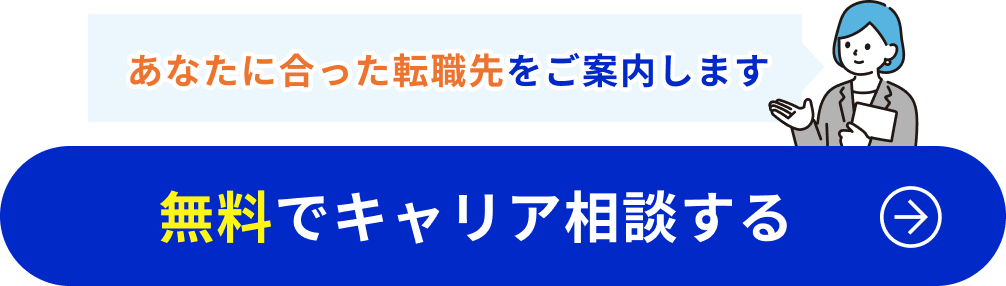未経験転職で可能性を広げよう!どこよりも求職者に寄り添ったキャリア支援のご相談はこちら!
「中卒だけど専門学校に行ける?」 東京で専門学校を探す20代向け。中卒からの入学条件、学費、就職支援、未経験転職成功の決め方まで、ツナグバが徹底解説。
この記事のキーワード#中卒専門学校 #キャリアアップ #奨学金制度
- #中卒専門学校 中卒でも進学可能な専門学校のこと。
- #キャリアアップ 専門学校を通じてキャリアを伸ばす方法のこと。
- #奨学金制度 学費を補助する奨学金や助成金制度のこと。
「中卒だと専門学校には行けないの?」「東京には学校が多すぎて、どう選べばいいのか分からない…」そんな不安を抱えている20代の方も多いかもしれません。ですが、中卒からでも専門学校への進学は可能であり、新しいキャリアを目指すための現実的な方法です。
この記事では、東京の専門学校選びで後悔しないための具体的な決め方を徹底解説します。入学条件、学費、奨学金、そして未経験からの転職成功まで、ツナグバがあなたの不安を解消し、未来を切り開く一歩をサポートします。
【中卒でも可能】東京の専門学校入学条件とキャリアアップの現実
「中卒だから、もう学ぶ機会はないんじゃないか…」「20代で未経験の分野に飛び込むなんて、遅いかな?」そう思っていませんか?実は、中卒から専門学校に進学し、新しいキャリアを築くことは十分に可能です。20代という若さは、新しい知識やスキルを吸収し、未経験の分野へ挑戦する上で、非常に有利な時期と言えるでしょう。

中卒者が専門学校へ入学するための具体的な条件
中卒を最終学歴とする方が専門学校に入学する方法はいくつかあります。 多くの専門学校では、入学資格として「高等学校卒業程度認定試験(旧大検)」の合格を定めています。
しかし、一部の専門学校では、「中学校卒業」を最終学歴とする方の入学を認めている場合もあります。この場合、「個別の入学資格審査」を設けていたり、入学願書受付時点で一定年齢以上(例:18歳以上)であることなどを条件としていることが多いです。
学校によって条件が異なるため、気になる専門学校の募集要項を必ず確認することが大切です。
専門学校で得られる実践スキルと就職実績
専門学校の大きな魅力は、実践的なスキルを短期間で身につけられることです。大学のように幅広く学ぶのではなく、特定の職業に直結する内容を集中して学べるため、卒業後すぐに働く力を養うことができます。
文部科学省の調査によると、専門学校では実習や演習の時間が多く、実践重視のカリキュラムが組まれています。さらに、最新のデータ(令和5年度)では、専門学校卒業生の就職率が80%以上と高い水準を維持しており、学んだ内容がそのまま就職に結びついていることが分かります。
こうした背景からも、中卒の方にとって専門学校は現実的で効果的なキャリアアップの道だといえるでしょう。
後悔しない!東京の専門学校選びで「失敗しない」3つの視点
東京は、数多くの専門学校が集まる日本の中心地です。選択肢が多いからこそ、自分に最適な学校を見つけるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

1. 通いやすさも重要!東京の専門学校「立地・アクセス」のメリット・デメリット
専門学校の立地は、日々の通学や学校生活の充実度に大きく影響します。
- 通いやすさ:毎日通うことを考えると、自宅からのアクセスが良いことは非常に重要です。公共交通機関の利便性や、最寄りの駅からの距離などを事前に確認しましょう。通勤ラッシュを避ける、乗り換えが少ないなど、ストレスなく通学できるかがポイントです。
- 都心の環境:東京の中心部に位置する学校であれば、最新のトレンドや情報に触れる機会が豊富です。例えば、ファッションやデザインの学校なら流行の発信地がすぐ近くにあり、ビジネス系の学校なら大手企業が集まるエリアでインターンシップの機会を見つけやすいといったメリットがあります。業界のプロフェッショナルとの交流イベントや、学外でのセミナー参加など、学びに繋がるチャンスも多いでしょう。ただし、都心は家賃や物価が高い傾向にあるため、生活費も考慮に入れる必要があります。
自身のライフスタイルに合った立地と環境の学校を選ぶことが、充実した学生生活を送るための第一歩です。
2. 「卒業後役立つ」東京の専門学校カリキュラムと専門性の見極め方
専門学校の最大の魅力は、実務に役立つ専門的な知識やスキルを習得できる点です。
- 専門性:自分が将来就きたい職業や、興味のある分野に特化した専門性の高いコースがあるかを確認しましょう。例えば、IT分野であればプログラミング言語やネットワーク、デザイン分野であればグラフィックツールやポートフォリオ作成など、卒業後すぐに現場で求められる実践的な内容が充実しているかを見極めることが大切です。
- 実務に即したカリキュラム:企業との連携によるインターンシッププログラムや、業界のプロフェッショナルが講師を務める授業など、卒業後に即戦力として活躍できる力を身につけるためのカリキュラムが整っているかを確認しましょう。実際に、文部科学省の調査(「学校基本調査」など)でも、専門学校では実習・演習に多くの時間が割かれており、実践的な学びを重視していることが示されています。
オープンキャンパスには積極的に参加し、実際に授業の様子を見学したり、在校生や卒業生の声を聞いたりすることも、カリキュラムの内容を深く理解する上で役立つでしょう。
3. 中卒者も安心!東京の専門学校が提供する「就職サポート」と「実績」
専門学校を選ぶ上で、卒業後の進路、特に「就職サポート」は非常に重要なポイントです。中卒から未経験の分野へ転職を目指す場合は、手厚いサポートがある学校を選ぶことが成功への近道となります。
- キャリア支援の充実度:履歴書や職務経歴書の書き方指導、模擬面接、企業説明会の開催など、就職活動に必要なサポートが手厚い学校を選びましょう。中には、個別カウンセリングを実施し、一人ひとりの適性や希望に合わせたきめ細やかな支援を行う学校もあります。
- 就職実績:学校のウェブサイトやパンフレットに掲載されている就職実績(就職率、主な就職先企業など)を必ず確認しましょう。これは、その学校の教育内容やキャリア支援の質を測る客観的な指標となります。特に中卒者向けの就職実績が明確に示されているかどうかも重要ですし、もし具体的な情報が少なければ、オープンキャンパスなどで直接質問してみるのも有効です。
就職活動は一人で行うものではありません。充実した就職サポートのある専門学校を選ぶことで、未経験からの転職もよりスムーズに進むでしょう。
【費用対策】東京の専門学校の学費と中卒者向け奨学金・助成金の活用法
専門学校への進学を考える上で、学費は大きな懸念材料の一つかもしれません。しかし、多くの専門学校では、学生の経済的負担を軽減するための様々な奨学金制度や助成金が用意されています。

1. 明確な「学費」内訳と卒業までの総費用把握
専門学校への進学を考える際は、学費の「総額」とその内訳を事前にしっかり把握することがとても重要です。学費は学校や専攻によって異なり、主に入学金・授業料・施設設備費・実習費・教材費など複数の項目で構成されています。
まずは、パンフレットや学校の公式サイトを使って内訳を丁寧にチェックしましょう。不明点がある場合は、学校の入試担当者や事務局に問い合わせることをおすすめします。
また、学費だけでなく、通学交通費や生活費(特に一人暮らしを検討している場合)も含めた「卒業までの総費用」を見積もっておくことが大切です。トータルの費用感を掴むことで、奨学金や助成制度の必要性も判断しやすくなります。
2. 中卒者も対象!賢く利用できる奨学金・助成金の種類
中卒から専門学校へ進学する際に使える代表的な制度には以下のものがあります
- 日本学生支援機構(JASSO)奨学金(給付型・貸与型)
→条件を満たせば中卒でも利用可。要申請。 - 国の教育ローン(日本政策金融公庫)
→親の収入などの条件あり。専門学校生も対象。 - 専門実践教育訓練給付金(厚労省)
→一定の雇用保険加入歴があれば、学費の最大70%が支給される。中卒でも社会人歴があれば利用可。 - 学校独自の奨学金や、地方自治体による助成制度
→東京や地元の自治体によって内容は異なるため、必ず個別に確認。
学費だけでなく、通学交通費や生活費も含めたトータル費用を把握し、制度を賢く活用しましょう。
まとめ:東京で中卒を活かす専門学校選びは「未来への投資」
中卒から東京の専門学校を選ぶことは、あなたのキャリアアップや未経験からの転職を後押しする現実的な「未来への投資」です。重要なのは、まず「将来のキャリア目標」を明確にし、それに合った専門性の高いカリキュラム、そして充実した就職サポートがある専門学校を慎重に選ぶことです。
東京という立地は、多様な学びの機会と就職のチャンスを提供しますが、学費の不安がある場合は、今回ご紹介した多様な奨学金制度や助成金を積極的に活用することで軽減できます。
中卒だからと諦める必要はありません。専門学校での学びは、あなたの可能性を最大限に引き出し、新しい未来を切り開くための具体的なステップです。ツナグバは、中卒から専門学校への進学、そして未経験転職を考えている20代のあなたを全力でサポートします。
この記事の監修

海老名 信行
取締役/COO
株式会社ツナグバ
大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
プロフィール紹介

 適職診断を受けてみる
適職診断を受けてみる